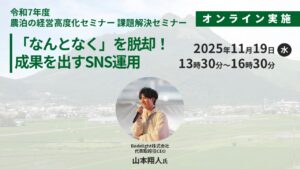「教育旅行の受入には興味があるけど、何が必要なのかわからない…」
「受け入れの担い手不足や高齢化で、継続が難しくなってきた…」
「学校や旅行会社に、地域の魅力をどうアピールすれば良いか悩んでいる…」
いま、教育旅行は大きな変革期を迎えています。「探究的な学習」や「SDGs」への関心の高まりを背景に、農山漁村地域での体験活動へのニーズは高まっています。これは、地域にとって関係人口を創出し、持続可能な地域経済を築く絶好のチャンスです。
一般社団法人全国農協観光協会では、農泊地域の経営高度化に向けた連続セミナーの第4回として、「農教育旅行の受入体制づくり」をテーマにしたセミナーを開催します。
今回は、北海道十勝で10年間に約2万3千人もの学生を受け入れた実践者・近江正隆氏と、国の施策にも精通し全国の事例を知り尽くす専門家・花垣紀之氏を講師にお迎えします。
「現場のリアルな実践知」と「全国で通用する普遍的なノウハウ」。この両輪から、教育旅行受け入れを成功に導き、「選ばれる地域」になるための具体的なヒントを学びます。
開催概要
開催日 2025年9月17日(水)13:30~16:30
方法 Zoomウェビナーを使用したオンライン開催
時間 13時30分~16時30分
※後日アーカイブ配信も行います。アーカイブ配信ご希望の方もお申込みフォームよりお申し込みをお願いいたします。
講師
今回講師にお招きしたのは、NPO法人食の絆を育む会 理事長 近江正隆氏と、財団法人都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流機構)グリーン・ツーリズムチーム長 花垣紀之氏です。
近江氏は元漁師という異色の経歴を持ち、北海道浦幌町の地域づくり「うらほろスタイル」を考案、実践しています。2012年にNPO法人食の絆を育む会を設立し、「とかち農村ホームステイ」事業を展開。10年間で約2万3千人もの学生を受け入れてきました。セミナーでは、「とかち農村ホームステイ」事業などの取り組み事例から、教育旅行受入のポイントや地域住民の心を動かし、行政や企業をも巻き込んだ地域の作り方を学びます。
花垣氏はグリーン・ツーリズム推進の第一人者として、長年、国の施策と全国の現場を繋いできたトップランナーです。昨年度農林水産省が制作した「農泊”教育旅行”受入手引き」にも有識者として携わり、教育旅行の最新トレンドを熟知しています。セミナーでは、全国の多様な事例分析に基づいた、安全管理、プログラム開発、学校へのアプローチなど、地域の体制づくりのヒントをお話しいただきます。
NPO法人食の絆を育む会のホームページはこちら→https://www.shokuhug.com/
財団法人都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流機構)のホームページはこちら→https://www.kouryu.or.jp/
講師プロフィール
近江正隆(おうみ まさたか)
1970年東京都目黒生まれ。19歳で単身北海道に移住し、酪農・畑作・林業・漁業に従事。1999年に漁業の傍ら、水産加工・ネット産直を開業し、楽天市場年間魚ランキング1位などを達成し、また数々のTVや雑誌などで取り上げられて、漁師直送の産直販売の草分け的存在となる。
しかし、2006年の漁船転覆事故での気づきなどから、漁師・水産加工・ネット産直を廃業し、働き方を大幅転換。2007年に地元浦幌町で「子ども若者が軸のまちづくり=うらほろスタイル」を考案し、同町の協働のまちづくりのカタチをつくる。また同時期に十勝管内19市町村の一次産業従事者と都市部の中高生を対象とした農村ホームステイ事業をスタートさせ、NPO法人食の絆を育む会を設立し、理事長に就任。コロナ前までの10年間で約2万3千人の学生を受け入れた。2019年に「うらほろスタイル」を補完し、税に依存しすぎない持続可能なまちづくりを目指すため、一般社団法人十勝うらほろ樂舎を創設。2024年より、新たな農村ホームステイのカタチを模索し、いのちを感じ、生きるを学ぶスタディーツアーを考案。食の絆を育む会の活動を復活させた。また2025年に「次世代の想いをベースにした社会づくり」に着手するために、一般社団法人SackOmiを設立。国連などと連携した「1億人のワールドチャレンジ」をスタートさせた。
花垣紀之(はながき のりゆき)
1971年、神奈川県川崎市生まれ。
1994年に(財)農林漁業体験協会に入職し、組織改編を経て、(一財)都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流機構)に勤務。2007(平成20)年度に、総務省・文部科学省・農林水産省による「子ども農山漁村交流プロジェクト(学校による農山漁村体験交流の推進等)」の普及に関わり、教育旅行民泊の受入地域協議会の登録制度の立ち上げを進めた。
学校教育による子供農山漁村体験交流に関する取組みや事例に精通しており、国・県等による子供農山漁村体験交流の専門家として就任する他、全国各地の農山漁村の受入整備等の指導・助言を行っている。
所属する団体では、国内旅行取扱管理者として、学校による教育旅行民泊等の手配型企画旅行を担当。近年では、私立中学校・高等学校のご依頼を受けて、受入地域と調整して「探究的な学習」に関連した現地学習を企画・手配を行っている。
2024(令和6)年度に内閣府「地域活性化伝道師」として登録される。
講義内容
<このセミナーでお伝えすること>
①農泊教育旅行のいま
教育旅行のトレンドは大きく変化しています。「探究的な学習」やSDGsを背景に、農山漁村での本質的な学びへの需要は急増。全国の事例に精通する花垣氏に、学校現場が今本当に求めていること、そして安全で質の高い受け入れを実現するためのポイントを解説いただきます。
②”うらほろスタイル”に学ぶ地域協働のカタチ
廃校の危機から10年で2万人超が訪れる地域へ。北海道浦幌町で「子どもが主役」の地域づくりを実践する近江氏。いかにして住民を巻き込み、行政や企業をも動かす「協働」の形を築いたのか。ゼロから始まった挑戦の軌跡から、単なる受け入れではない、持続可能な地域づくりのヒントを探ります。
③持続可能な受入体制の構築~価値を生むプログラムと未来を担う人材育成~
受け入れは「人」と「プログラム」が生命線。一過性のイベントで終わらせず、次世代に繋がる仕組みをどう作るか。地域の資源を「教育的価値」に変えるプログラム造成術と、住民が主役となり活動を担う人材育成の具体的な手法について、両講師の視点から掘り下げます。
参考(農泊”教育旅行”受入の手引き)
昨年度、農林水産省では、農泊地域における教育旅行の受入のポイントを纏めた手引きを作成しています。本セミナー講師の花垣氏も有識者として制作に携わっております。
事前に目を通すことで、セミナーでの学びも深まります。ご自身の地域の課題解決のヒント探しに、ぜひご活用ください。
閲覧はこちらから→https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/attach/pdf/nouhaku_top-114.pdf